- 愛猫のトイレの回数が気になる
- 猫の平均的なトイレ回数を知りたい
- 猫の健康状態をトイレから判断したい
猫を飼っていると、愛猫のトイレの回数が気になることがあります。正しい回数がわからず、不安を抱える飼い主さんも多いです。
トイレ回数は、猫の健康状態を知る指標です。
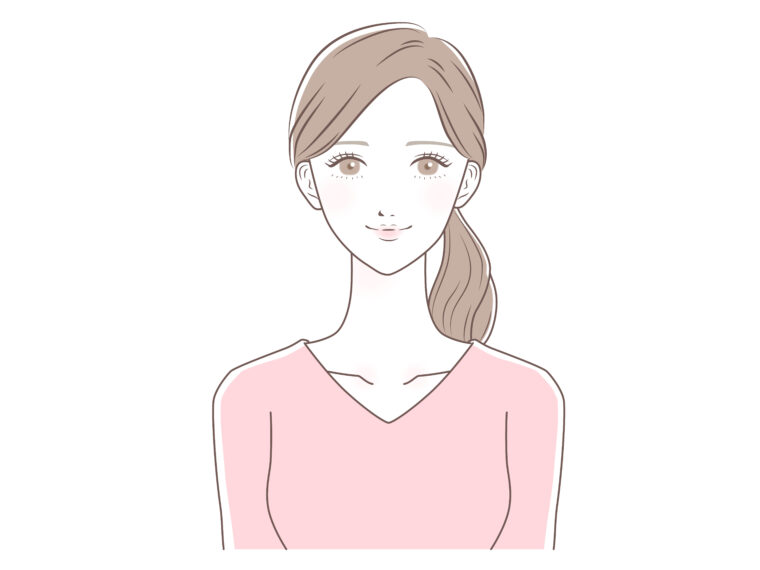
我が家の主治医は、猫のトイレは膨大な情報の宝庫なんだよ!!と常々おっしゃっています
この記事では、猫のトイレの平均回数、多い場合・少ない場合の原因と対処法、病気を発見するヒントを解説します。
» 猫の飼い方を解説
猫のトイレから健康状態を判断する方法がわかり、適切なケアができるになりますので最後まで読んでいただけると嬉しいです。
筆者のプロフィールが気になる方はこちらをチェックして下さいね。
→ペット用品店勤務 TOMOMIの詳しいプロフィール
猫のトイレの平均回数

健康管理のため、普段のトイレ回数を把握し、急な変化があれば獣医師に相談しましょう。
» 猫のストレスサインの見分け方
おしっこの平均回数
猫のトイレの回数には人間同様に個体差がありますので、厳密に「〇回が正解」というものはありませんが、健康な成猫の1日のおしっこの平均回数は2〜4回程度、子猫は成猫より回数が多く4~5回程度です。
とは言え、個体差や生活環境によって1〜5回の幅があるのが一般的です。おしっこの回数は以下の要因で変動するため、平均と異なっても必要以上に心配はいりません。
- 水分摂取量
- 食事内容
- 季節
- 気温
- ストレス
- 環境の変化
多くの猫は朝晩の2回おしっこをする傾向にあり、1回のおしっこ量は約20〜30ml程度です。年齢によっても変化し、子猫や高齢猫は回数が増える傾向です。尿量や回数の急激な変化は病気のサインの可能性があります。愛猫の排尿パターンを把握し、変化に気づいたら注意して観察しましょう。
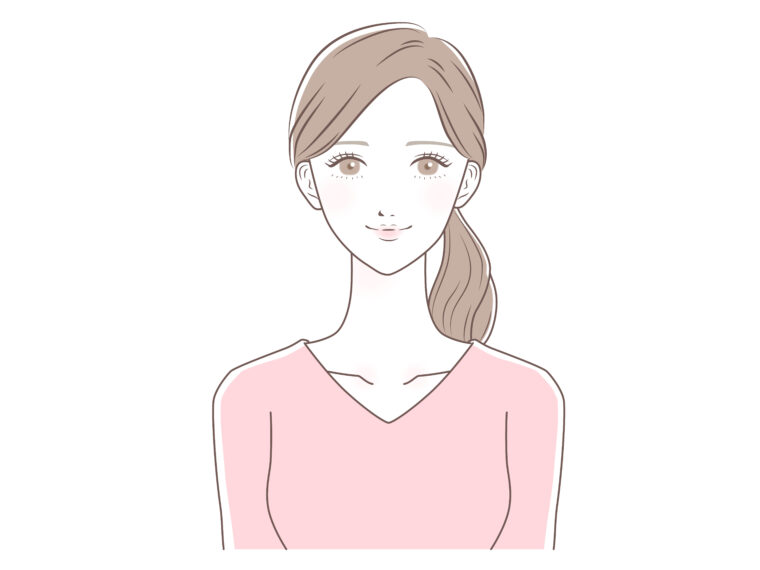
普段より多いかも?少ないかも??という基準を知っておくことが何より大切になので、今日からでも記録しておくことを強くおすすめします。
うんちの平均回数
正常な排せつリズムを持っている健康な成猫であれば、うんちの平均回数は1日1〜2回程度です。子猫の場合は消化器系がまだ発達途中であるため、1日3〜4回程度と成猫よりも頻度が高くなります。
回数は以下の要因で変動します。
- 個体差
- 生活環境
- 食事の量や質
- 運動量
- ストレスレベル
- 年齢
固形物の排せつがない日が1〜2日続くのは正常範囲内です。3日以上排便がない場合は、便秘の可能性があるので注意深く観察しましょう。うんちの量や硬さ、色や臭いなども重要な指標です。急激な回数の増減や異常な便の状態は、病気のサインの可能性があるため注意しましょう。
猫のトイレの回数が多い原因と対処法

猫のトイレ回数が増える原因には、ストレス、不安、病気、食事の問題などがあります。おしっことうんちの回数によって、関連する病気が異なります。トイレ回数が増えたときには、適切な対処が必要です。対処法を試しても改善が見られない場合は、獣医師に相談しましょう。
» 猫のご飯選びのポイント
» 猫が頻繁にトイレに行く場合に考えられる病気と回数の目安
おしっこの回数が多い場合
おしっこの回数が増える原因はいくつかあります。一般的に多いとされている病気は、尿路感染症や膀胱炎などがあり、頻尿や排尿時の痛みも現れます。糖尿病や腎臓病、甲状腺機能亢進症の初期症状でも、頻尿の傾向がみられる様です。体内の水分バランスが崩れるため、おしっこの量が増えやすくなります。
尿路に何らかの病気の症状がある場合、排尿時に痛みを感じるためトイレを我慢してしまう傾向があります。高齢猫の場合は、腎機能の低下によっておしっこの回数が増える場合もあります。腎臓病の初期症状として、多飲多尿になるケースもあるので注意が必要です。
意外かもしれませんが、ストレスや不安も水分摂取量が増加するので頻尿の原因になります。新しい環境や家族の変化など、猫にとってストレスとなる出来事があった場合は回数や量を注意して観察してあげる必要があります。
利尿作用のあるフード、サプリや薬の影響で、一時的に頻尿になる場合もあります。新しいフードに変えたり、サプリや薬を飲み始めたりした後に頻尿が起きた場合は、それらの影響も疑いましょう。頻尿の原因はさまざまで、一概に判断するのは困難です。
» おすすめのキャットフードの選び方を解説!
長期間続く場合や、他の症状を伴う場合は、迷わずに獣医師に相談しましょう。早期発見・早期治療が猫の健康を守るうえで重要です。
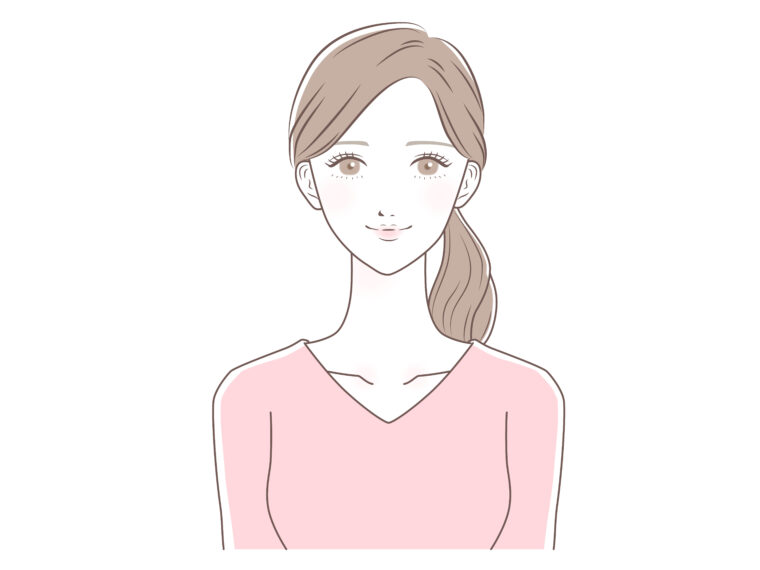
うちの保護した猫も、あまりに多くの水(1日に400ml以上!)を飲んで頻尿もすごいので尿検査と血液検査しました。結果、数値に異常はなく、緊張によるストレスと診断されました。
うんちの回数が多い場合

うんちの回数が多くなる原因は、次のようなものが考えられます。
- 食事量の増加
- フードの変更
- 消化不良
- 食物アレルギーや不耐性
- 腸内フローラの乱れ
- 大腸の炎症や腫瘍
ストレスや不安から、腸内が過敏になると回数が増えやすくなります。薬の副作用でうんちの回数が増えるケースもあるため、新しい薬を飲み始めた場合も注意して観察しましょう。
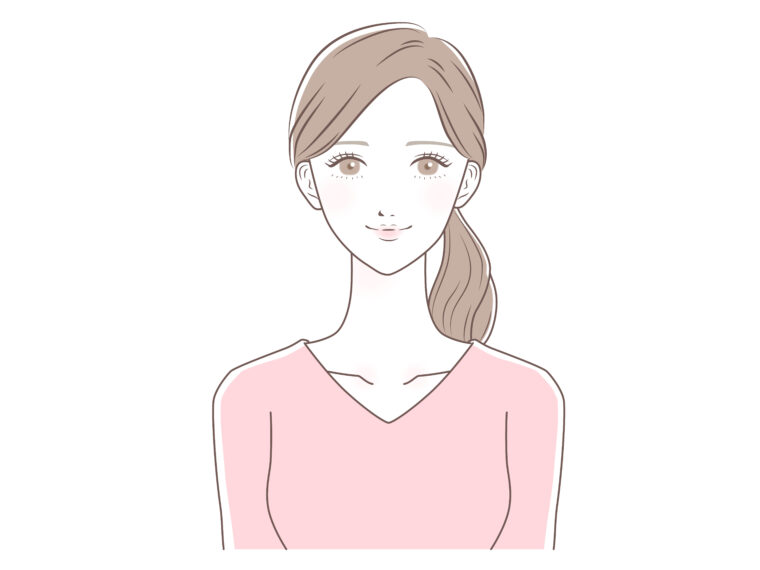
フードによって便の様子は変化するよ。例えば、食物繊維の多いフードなどに変えたら回数と量が増えたという声もあるよ。
軟便や下痢の様なうんちの増加は、腫瘍や腸の異常が原因の場合もあります。長期間続く場合は、ためらわず獣医師に相談しましょう。
» 猫の適切なご飯の量を解説
トイレ回数が増えたときの対処法
トイレの回数が増えている場合、まずは以下のような対処法を試しましょう。
- 室温が高すぎていないか確認
- 猫トイレの清潔を保つ
- 猫砂を変えてみる
- トイレ周辺の温度にも気を配る
- 違う形状のトイレを追加し選択肢を増やす
- 食事内容や回数を見直す
- 運動量を増やす
猫の体調を整えるためには、適切な水分補給が欠かせませんが、室温が高すぎることが原因で水を大量に飲んだ結果、頻尿になっている可能性もあります。
夏なら熱中症対策、冬は室温を適温に保ち、猫が快適に過ごせる室温になっているかを再確認しましょう。
猫はトイレ環境が好みでないと我慢して膀胱炎になり、結果的に頻尿になることも多いです。猫トイレは常に清潔に保ち、好むトイレの形状、猫砂を探してあげましょう。
便秘で便の回数が少ないなら水分の多いウエットフードを増やしてみましょう。
運動量が少ないと腸の動きも悪くなりますので、1日15分でもよいので一緒に遊ぶ時間を設け体を動かしてあげましょう。
症状が改善しない場合は、まよわず動物病院を受診しましょう。
排尿時の様子を観察し、痛がっていないか確認するのも重要です。尿の色や臭いの変化にも注意を払いましょう。飼い主さんだけが分かる変化ですので、異常の早期発見につながります。
» 猫のトイレ掃除の重要性や掃除方法、臭い対策について詳しく解説
» 健康と幸せのために!猫にあげていい食べ物と正しい食事の管理法
猫のトイレの回数が少ない原因と対処法

猫のトイレ回数が減る原因と対処法を解説します。猫の様子をよく観察し、適切な対処法を実践しましょう。
おしっこの回数が少ない場合
おしっこの回数が少ない場合、健康問題が考えられます。以下の症状があれば、早めに獣医師に相談しましょう。
- 水を飲む量が減った
- 食欲が落ちた
- おしっこをするときに痛がる様子が見られる
- 尿の色が濃くなった
おしっこの回数が減る主な原因として、脱水症状や尿路の問題が考えられます。脱水症状は、水分摂取量の減少や食欲不振によって起こるのがほとんどです。猫が十分な水分を摂取できていないと、体内の水分を保持するために尿量が減少します。尿路の問題としては、尿路結石や膀胱炎、尿道炎などが挙げられます。
おしっこの回数が減っている原因を見つけ、早めに適切な対処をすれば、猫の健康を守れます。日頃から猫の様子をよく観察し、変化に気づいたら迅速に対応しましょう。
うんちの回数が少ない場合

うんちの回数が少ない場合は便秘になっている可能性があります。
とは言え、毎日出ないから便秘というわけではなく、2日に1回出ていれば問題ありません。ただ、かなり力んでいる様子があれば、排便に困難な状況かもしれません。猫の健康に悪影響を及ぼすため注意をしてあげるが必要があります。
便秘の原因は、主に以下のようなものが考えられます。
- 食事量の減少や食欲不振
- 水分摂取量の不足
- 運動不足
- ストレスや環境の変化
- 食物繊維の不足
食事内容を見直したり、水分をこまめに与えたりすると改善できる場合があります。便秘が続く場合は、深刻な健康問題が起こっている可能性もあるため注意してください。腸閉塞や甲状腺、腎臓病などの病気が隠れている場合もあるので、迷わず獣医師に相談しましょう。
» 猫の運動不足のリスクと対策
猫砂が合わなかったり、トイレの場所が不適切、清潔でなかったりすると、猫は長く滞在したくなくなるのでうんちの回数が減ります。トイレの環境を整え、日々のケアを欠かさずに行いましょう。
トイレ回数が減ったときの対処法
トイレ回数が減った場合、まず水分摂取量を増やします。新鮮な水を常に用意したり、ウェットフードを与えたりする対処法が効果的です。水飲み皿を複数設置したり、食事内容を見直したりするのもおすすめです。
» 猫にウェットフードを与えるメリットとデメリットを解説!
高繊維食を取り入れると腸の動きが活発になり、排便を促進できます。野菜を含むキャットフードを選んだり、少量のカボチャやさつまいもを与えたりするなど食事の内容も工夫も良いです。高繊維のサプリメントを使用するのも対処法の一つです。
ストレス要因を取り除くのも重要です。猫は敏感な動物なので、環境の変化やストレスがトイレの回数に影響を与えます。静かで落ち着く場所にトイレを設置したり、新しいおもちゃで遊びの時間を増やしたりすれば、ストレス解消ができます。
規則正しい生活リズムを作るのも効果的です。適度な運動も排せつを促進する効果があります。室内で飼育している猫は運動不足になりやすいので、遊びを通じて体を動かす機会を作りましょう。
トイレの回数や排せつ物から猫の病気を見つけるヒント

猫の健康状態を知るうえで、トイレの様子は、健康状態を知る手がかりです。以下の2つを観察すれば、早期に病気の兆候を見つけられる可能性があります。
- 尿や便の色や形状
- 排せつ時のしぐさ
変化に気づいたら、早めに獣医師に相談しましょう。
尿や便の色や形状
尿や便の色や形状は、猫の健康状態を知る重要な手がかりになります。普段と異なる以下のような特徴が見られたら、病気のサインの可能性があります。
- 尿の色・量の異常
- 血尿・血便
- 便の色・形状の異常
- 便に混じる異物(寄生虫など)
- 便の量の異常
- 尿や便の異臭
毎日のトイレチェックを行い、早期発見・早期治療につなげましょう。愛猫の排せつ物の状態を確認する習慣をつけてください。
排せつ時のしぐさ
排せつ時に異常な行動が見られる場合は、病気の可能性があるので注意が必要です。以下のようなしぐさが見られる場合は、猫が健康に問題を抱えている可能性があります。
- 苦しそうな表情を見せる
- 長時間トイレに滞在する
- トイレ内で鳴く
- 頻繁にトイレへ行く
- トイレ外での排せつがある
- 排せつ後の痛みがある
- トイレを回避する
- 排せつ時の体の震えがある
- 異常な舐め行動がある
- トイレ内で落ち着かない
排せつ時に痛みや不快感を感じていると、行動として現れます。普段と違う行動が続く場合は早めの対処が大切です。泌尿器系や消化器系の疾患を引き起こしている可能性もあるため、自己判断はしないで獣医師に相談しましょう。
猫がトイレをする回数の変化に気づいたときの対処法

猫のトイレ回数に変化があった場合、適切な対応が重要です。家庭でできるケアや獣医師に相談するべきタイミングについて理解し、必要に応じて獣医師に相談しましょう。
家庭でできるケア
猫のトイレ回数の変化に気づいたら、家庭でできるケアを試しましょう。家庭でできるケアとして、以下の方法があります。
- 水分摂取量を増やす
- 食事内容を見直す
- ストレス要因を取り除く
- トイレの清潔さを保つ
- トイレの数や配置を調整する
猫用のサプリメントを与えたり、適度な運動を促したりするのもおすすめです。定期的な体重測定や排せつ物の観察、快適な環境作りも改善につながります。症状が長引く場合は、獣医師に相談しましょう。
» 猫のトイレの理想的な場所選びを解説
獣医師に相談するべきタイミング
猫のトイレの回数に異常を感じたら、獣医師に相談します。以下のような症状が見られる場合は、早めに受診しましょう。
- 排尿・排便の回数の変化
- 血尿・血便
- 排せつ物の色・臭いの変化
- トイレ時の痛がる様子
- 排せつ量の異常
- トイレの失敗増加
- 排せつ困難
- 食欲・飲水量の変化
- 体重の急激な変化
- 行動や様子の変化
早めの相談することで適切な治療を受けられ、重症化を防げます。
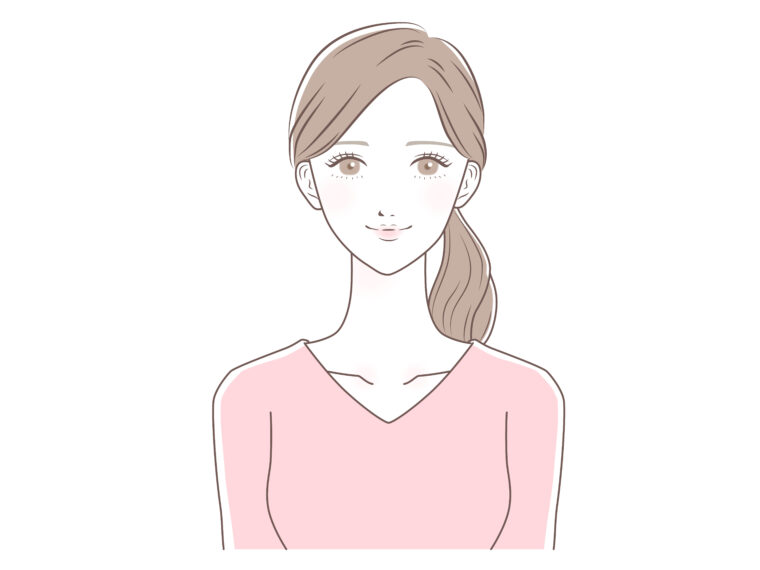
何と言っても、猫の健康維持には飼い主さんの観察力と迅速な対応が欠かせません。
愛猫の変化に一番詳しいのは主治医ではなく、飼い主さんです!!
» 猫の粗相の解決方法
» 理由はさまざま!猫が突然トイレで排泄しなくなる原因と対策
猫がトイレをする回数のよくある質問

猫のトイレの回数に関するよくある質問にをまとめました。猫のトイレ回数が気になる方は参考にしてくださいね。
季節や気温の変化はトイレの回数に影響する?
季節や気温の変化は、猫のトイレの回数に影響を与えます。夏は水分摂取量が増えるため、おしっこの回数が増える傾向です。トイレの回数に影響を与える季節や気温の変化の要因は次のとおりです。
- 夏季の飲水量の増加
- 室温が高い部屋での飲水量増加
- 急激な気温変化
- 季節の変わり目
- 冬季の活動量減少
エアコンによる室内環境の変化も、トイレの回数に影響を与える場合があります。季節による食事内容の変化も排せつ回数に影響を与えます。季節によるトイレの回数の変化は一時的なものが多いですが、長期的な変化や急激な変化が見られる場合は注意が必要です。
» 猫にとって快適な室温は?季節別の室温管理方法を解説
» 猫との生活でエアコンを使うポイント:季節別の適切な温度を解説
年齢を重ねるとトイレの回数は変わる?
年齢を重ねるとトイレの回数は変化します。高齢猫は若い猫と比べて腎臓機能が低下し、排尿回数が増加する傾向です。
排尿回数の増加や排便回数の減少、水分摂取量の減少、代謝の低下などは、高齢猫の特徴としてよく見られる変化です。
加齢による筋力低下や消化機能の衰えにより便秘になりやすく、排便回数が減少する場合もあります。関節炎などの身体的な問題により、トイレ行動が変化する可能性も考えられます。高齢猫の認知機能の低下により、トイレの場所を忘れるのもまれに見られるケースです。
年齢による変化は個体差が大きいので、定期的な観察が重要です。愛猫のトイレ回数に変化を感じたら、獣医師に相談しましょう。
まとめ

猫のトイレ習慣の理解と適切な管理は、飼い主さんにとって重要な任務です。猫の健康状態を把握するために、トイレの回数や排せつ物の状態を日常的に観察しましょう。トイレの回数が多い場合や少ない場合の原因を理解し、適切な対処法を知っておくのも重要です。
平均的な回数や排せつ物の色・形状、様子にも注意を払い、異常を感じたら獣医師に相談してください。季節や年齢によるトイレ回数の変化は正常な場合もあるので、継続して観察しましょう。日頃からよく観察し、変化に敏感になれば、安心して愛猫の健康を守ることができます。















